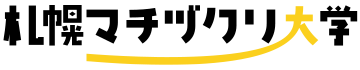2025年9月23日(土)、札幌マチヅクリ大学のゼミ活動が開催されました。この日は、講義とワーク、そして映像制作を通じて、ガクセーたちは“まちづくり”を自らの視点で捉え、形にしていく1日となりました。
■ 1講目 本日のプログラムと目標設定
午前の冒頭では、マチヅクリ大学コーホー課長・千葉里美さん(北海商科大学准教授)から、本日の流れと目的が共有されました。今回のゼミは、前半の講義で“発想の方法”や“まちづくりの視点”を学び、後半はフィールドワークも交えながら、各ゼミで“表現と編集”の実践へとつなげる構成となっていました。「自分たちのゼミのコンセプトを、どんな言葉と映像で伝えられるか」を考える一日となりました。


■ 2講目 課題解決の方法論 ― 右肩下がりの時代のまちづくり
講師は、マチヅクリ大学キャリア課長であり札幌大谷大学准教授の丸山宏昌さん。丸山さんは、人口減少が続く社会の中で「問題解決型」から「ありたい姿を描くポジティブアプローチ」が注目されていることを紹介。右肩上がりの時代のように“原因を追って対処する”のではなく、“望む未来を起点に考える”姿勢が重要だといいます。
また、「仮説思考」や「ゼロベース思考」を軸に、現場で生まれる“声なき声”に耳を傾ける姿勢の大切さも強調しました。解決策を立てる際には「Why(なぜ)」と「Who(誰が)」を明確にし、目的・目標・計画を区別して考えることが重要だと説明。人口減少社会を悲観ではなく「新しい価値を再構築するチャンス」として捉える発想が印象的でした。


■ 3講目 グループワーク映像づくり ― ストーリーを伝える撮影と編集の技術
続いて、マチヅクリ大学キカク課長であり有限会社テックワークス代表の鈴木卓真さんによる講義が行われました。鈴木さんは、「映像はストーリーを伝えるためのデザイン」と語り、構図や編集の基本を実践的に解説。撮影では“三分割法”を用いて、被写体の配置や余白のバランスからストーリー性を生み出す方法を学びました。
また、編集の流れを「コマ割り → トランジション → 音楽 → テキスト」の順に整理。音楽の選定や著作権への配慮、フェードイン・アウトの使い方など、実践的なポイントも多く紹介されました。
「技術よりも“誰に何を伝えたいか”を明確にすることが大切」というメッセージに、ガクセーたちは熱心に耳を傾けていました。


■ 4講目 自分事のまちづくり ― 自分と社会をつなぐために
マチヅクリ大学でありキョーイク課長である北海道教育大学准教授の酒井秀治さんは、「まちづくりは自分の好きなことや興味からしか始まらない」と語ります。社会課題から出発するのではなく、自分の関心と社会の接点に“まちづくりのタネ”があるという視点を提示しました。
酒井さんが実践する「都市型養蜂」や「リノベーションまちづくり」などの事例は、まちと人をつなぐ創造的な活動として紹介されました。また、「自分のこだわりを少し外に開く」ことで共感が生まれ、それがやがて“シビックプライド(まちへの誇り)”へとつながると語ります。
「与えられた枠ではなく、自分の軸と余白を持つこと」が、まちづくりを継続するエネルギーになるという言葉が印象的でした。


■ 5講目 グループワーク・映像制作実践
午後からは、これまでの学びをもとに、ゼミごとでのグループワークを通じた映像制作に挑戦しました。学生たちはそれぞれまちに出て、建物や人、風景などの素材を撮影し、各自のカメラやスマートフォンで編集を進めました。
マチヅクリ大学のスタッフが個別にサポートを行いながらも、構成・撮影・編集のすべてを学生主体で進めるスタイルです。講師陣からのアドバイスを受け、音楽やテキストの入れ方を工夫し、試行錯誤しながら作品を形にしていきました。

■ 6講目 発表 ― まちを伝える自分たちの視点
1日の締めくくりは、各ゼミによる映像発表です。完成した作品は、それぞれのゼミのテーマを中心に、創成イーストエリアの人々や場所に焦点をあてたもの、まちの音や空気感を重視したものなど、それぞれが個性と視点の違いを生かした内容となりました。
発表後は講師から講評があり、構図や編集技術だけでなく、「まちをどう見て、どう伝えようとしたか」という姿勢についてもコメントが寄せられました。




■ まとめ
この日は、「課題を解決するだけではなく、ありたい姿を描く力」「社会を変える前に、自分の“好き”や“興味”から始めること」そして、「その思いを伝えるための表現力」など、講義と実践を通じて学び、考えた1日となりました。今後のまちづくり活動の礎となるような内容だったのではと思います。